借地権とは、第三者(地主)から土地を借りてその対価(地代)を支払い、借りた土地に建物を立てられる権利をいいます。「土地・建物の両方を所有する」ケースを所有権と言いますが、借地権の場合は「①建物は所有②土地の所有者は第三者(地主)」という点が大きなポイントです。
「物件広告を見ていたら、同じ区画なのに一棟だけ格安な建売を見つけた!」
「お手頃価格だと思って調べてみたら“借地権”と書かれてあった」
…など、さまざまな場面で借地権が絡む物件を目にしたり、借地権という言葉を目にしたりする機会はあるでしょう。
借地権は土地を購入するわけではないため、同じ面積や築年数などで比較すれば、所有権のある物件よりも借地権付き物件のほうが販売価格が安い傾向にあります。購入金額が低い分、住宅ローンの支払い負担も軽減されるメリットもあるでしょう。
とはいえ借地権にはさまざまな制約があり、決してメリットばかりとは言えません。もしも借地権付きの物件を検討しているなら、借地権の種類や法律上の仕組みを理解しておくことをおすすめします。
この記事では、借地権の概要や種類、メリットやデメリットについてわかりやすく解説します。
借地権の種類

借地権には「地上権」と「賃借権」と呼ばれる2種類が存在します。権利の強さや地代の発生などにも大きな違いがあるので、まずはそれぞれの違いについてチェックしておきましょう。
| 地上権 | 賃借権 | |
| 権利の種類 | 物権 | 債権 |
| 存続期間 | 半永久的 | 20年(更新可) |
| 地代 | ルールはない | 必要 |
| 売買 | 地主の承諾が必要 | 地主の承諾が必要 |
| 登記 | 地主に登記義務はない | 地主に登記義務がある |
地上権と賃借権の大きな違いは、物を直接使う権利である「物権」と、人を介して使う権利である「債権」です。
「物権」は、家や車などの財産を支配できる権利であり、すべての第三者に対して自分の所有物であると主張する権利を持っています。
たとえば住宅(土地+建物)の場合、売却すると所有権も一緒に移るのが特徴です。
また、一度設定するとそのものの上に同じ物件を設定できないのもポイントです。住宅の場合、土地の所有権が登記簿謄本上に登記(設定)されれば、他の人は登記することができないため所有権を設定できません。
一方「債権」は特定の人に特定の行為を請求できる権利を言います。これは第三者の誰にも主張できるわけではなく、債権者にのみ主張できるのがポイントです。
また物件とは異なり、同じものの上に複数設定できるのも債権の特徴です。
債権は契約や法律に基づいて発生するため、契約書を取り交わした時点で債権者(借主)と債権者(貸主)という立場が生まれます。
独占的である物権に対し債権は独占的ではない権利のため、多くの住宅は地上権(物権)よりも賃借権(債権)が発生するケースが一般的です。
ここで“土地を所有するA”と、その“土地の借地権を求めるB”の立場を踏まえ、地上権と賃借権の違いについてさらにくわしく解説します。
地上権とは
Aの所有する土地をBが借りる契約を交わし、地上権の行使が確定すると、借主であるBは土地を自由に利用することができるため、A(地主)の許可を取らなくても住宅を建てることができます。
また地主であるAに登記義務はないため、借主側が登記簿謄本上に地上権を登記でき、第三者へ権利を主張することができます。地上権を設定すれば抵当権を設定することもできるため、Bは住宅ローンを組みやすいというメリットが生まれるのです。
さきほど“住宅の場合は地上権(物権)よりも賃借権(債権)が発生するケースが一般的”と説明しましたが、これはAにとって賃借権よりも地上権のほうがデメリットが大きいことが関係しています。
というのも、地上権の存続期間は30年間以上(最短30年)と決まっており、Bはこの期間中に地上権の土地を自由に扱うことができます。逆に、Aにとっては最低30年間も自分の土地を自由に使うことができないのです。単純に言えば自分(A)よりも借りた側(B)の権利が強くなるため、Aが不利になりやすく、住宅の場合は地上権ではなく賃借権が設定されることが一般的です。
土地の賃借権とは
賃借権は、賃貸借契約を交わすことで賃料(地代)が発生するのが大きなポイントです。賃借権=債権であることから、債務者であるBは債権者であるAに対し賃料を支払う義務が発生します。
もちろん地上権と同じように、Aが所有する土地にBが建物を建てることはできます。ただしBにとっては地上権よりも自由度が少なく、建物を建てたり取り壊したりするには賃借人であるAの許可が必要です。
また賃借権の存続期間は20年以下であり、登記義務はありません。とはいえ、借地借家法が適用されれば最短30年になります。地上権と賃借権の違いに加え、法律(旧借地法・新借地借家法)に関する情報を理解しておけば、トラブルを回避することができるでしょう。
旧借地法と新借地借家法の違いとは?

借地に関するトラブルは数多く発生しています。たとえば、土地の有効活用や売却を目的とした明け渡し要求を巡るトラブルや、地代の増減を巡るトラブルです。
こうしたトラブルに対し、借地権には「旧借地法」と「新借地借家法」と呼ばれる法律が存在します。
まずはそれぞれの違いについてくわしくご紹介しましょう。
旧借地法とは
| 旧法借地権 | |||
| 堅固建物 | 非堅固建物 | ||
| 当初の存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
| 当事者による期間の定めがない場合 | 60年 | 30年 | |
| 更新後の存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
| 当事者による期間の定めがない場合 | 30年 | 20年 | |
賃借権を設定する際の存続期間は30年、更新後は20年と決まっています。旧借地法は建物を以下の2種類に区分しており、それぞれで設けられている期間が異なるのも大きなポイントです。
- 堅固建物…石造・土造・レンガ造・コンクリート造・ブロック造など
- 非堅固建物…木造など
この期間中は借地権を行使した側が法律上強く守られており、地主側の更新拒絶や建物明け渡し、更地返還などは正当な理由なしに認められません。
ただし、更新後の存続期間中に建物が朽廃した場合の借地権は消滅するため注意が必要です。
新借地借家法とは
新借地借家法は、法定更新される「普通借地権」と法定更新を排除する「低地借家権」があります。そのうちの普通借地権の存続期間については以下の通りです。
| 普通借地権(新法) | |||
| 堅固建物 | 非堅固建物 | ||
| 当初の存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | |
| 当事者による期間の定めがない場合 | 30年 | ||
| 更新後の存続期間 | 存続期間 | 1回目の更新20年以上それ以降の更新10年以上 | |
| 当事者による期間の定めがない場合 | 1回目の更新20年それ以降の更新10年 | ||
普通借地権の大きな特徴は、旧法と違って堅固建物と非堅固建物の区分がなくなったこと、そして旧法のように法定更新が可能な点です。
対する定期借地権は、法定更新ができず期間満了とともに借地権利者は土地を更地にして地主に変換しなければならない義務があります。
また、定期借地権にも大きく分けて3つの種類が存在します。
- 一般定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
- 事業用定期借地権
一般借地権はおもに分譲マンションなどで使われることがあり、借地権の存続期間を50年以上として設定されるのが特徴です。期間満了に伴い借地権契約は終了するため、借地権者は建物を解体したうえで土地を地主に返還しなくてはなりません。
建物譲渡特約付借地権は存続期間が30年とされており、期間満了時に地主が建物を買い取ることがあらかじめ約束されています。しかし、地主にとって借地権終了時に古い建物を購入すること自体メリットが少ないため、建物譲渡特約付借地権はほぼ利用されることがありません。事例としては、倉庫や工場などがあります。
事業用定期借地権はコンビニやスーパー、ドラッグストアなどの商業施設などで利用される借地権で、期間満了時には借地人が建物を取り壊し、更地返還しなくてはなりません。契約期間や収益性から、定期借地は事業用定期借地権の利用がもっとも普及しているのが特徴です。
そしていずれの定期借地権においても、借地権の更新や建物買取請求権などは認められていません。つまり、新借地借家法における借地法はこの定期借地権を指すことがほとんどなのです。
借地権のメリット

借地権のメリットは以下の3つが当てはまります。
- 税金の負担が少ない
- 低コストで土地を利用可能
- 借地契約の期間終了後も更新できる
土地を所有するだけで発生する税金は所有者である地主に課せられるため、土地と建物を両方所有するよりも税負担が少ないです。また借地契約の期間や条件も、交渉次第で柔軟に設定できるのも嬉しいポイントと言えるでしょう。
では、3つのメリットについて詳しく解説します。
税金の負担がない
借地権における税金の大きな特徴は、土地に関する税負担が発生しないことです。
地方税法により、土地に対する固定資産税や都市計画税は、土地所有者である地主に課税されます。これらの税金は土地の所有者が負担する義務を負うため、借地権者は支払う必要がありません。
ただし、借地権者が建物を所有している場合は別です。借地権者は自身が所有する建物に対して、固定資産税と都市計画税を納める必要があります。
これらの税金は毎年課税され、土地の税金とは別に、建物の評価額に基づいて計算されます。
納付は年4回に分けて行うことが一般的です。このように、借地権者の税負担は建物に限定されるため、土地所有の場合と比べて税負担を抑えることができます。
低コストで土地を利用可能
借地権の最大のメリットは、土地を購入せずに利用できることで、初期費用を大幅に抑えられる点です。
借地権付きの建物価格は、土地・建物の所有権付き物件と比べて、通常6〜8割程度安く設定されています。
これは、土地の取得費用が不要なためです。
代わりに借地権者は、土地所有者に対して毎月または毎年の地代を支払う必要があります。
地代は土地の相続税路線価などを基準に算出され、一般的に年額で土地価格の数パーセント程度となります。
特に地価の高い都市部では、土地を購入する場合と比べて初期投資を大きく抑えることができ、住宅ローンの借入額も少なくて済みます。
このため、土地所有にこだわらない方にとって、現実的な選択肢となっています。
借地契約の期間終了後も更新できる
借地権には契約期間が設定されていますが、借地借家法により、期間満了後も原則として契約を更新することができます。これは借地権者の権利を保護するための重要な規定です。
更新を拒否できる地主の「正当な理由」とは、土地を自己使用する必要性が生じた場合や、借地権者に債務不履行などの重大な契約違反がある場合に限定されています。そのため、地代の支払いを適切に行い、契約条件を守っている限り、借地権者は安定して土地を利用し続けることができます。
ただし、定期借地権は契約期間満了後の更新が一切認められない借地権です。これは契約時に期間満了での更新なしを合意する特殊な契約形態となっています。そのため、契約の種類を確認し、将来の計画を立てることが重要です。
借地権のデメリット
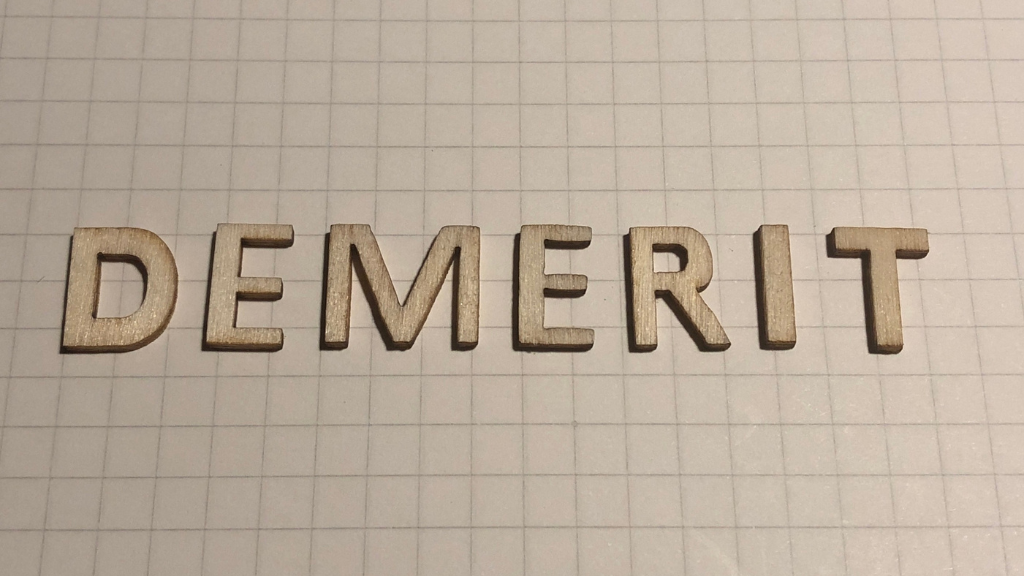
借地権はあくまで土地を借りている状態であり、自分(賃借人)の所有物ではありません。したがって、借地権には以下のデメリットが生じます。
- 地代を払っても自分の試算にならない
- 地代や更新料がかかる
- 第三者への売却が困難
借地権を行使して住宅を建てた(または購入した)場合、将来的な増築や大規模なリフォームが自由にできませんし、地代や更新料を払い続けなくてはなりません。ここで、借地権の3つのデメリットについて詳しく解説します。
地代を支払っても資産にならない
借地権はあくまで土地を借りている状態であり、所有者は地主にあります。つまり、地代を払い続けても所有者が変わることはなく、借地人の資産にはなりません。加えて、大規模なリフォームや建て替えには地主の承諾が必要になります。所有権よりも圧倒的に自由が少ないのが、借地権の大きなデメリットと言えるでしょう。
地代や更新料がかかる
借地権付きの建物は、地主に対し毎月地代を支払わなくてはなりません。また、契約更新の際は更新料が発生する可能性もあります。借地権の更新料に支払い義務はありませんが、契約内容によっては更新料を負担しなくてはならないため注意が必要です。
また土地を借りている間に地価が上昇した場合や、地主に正当な理由がある場合には、更新時に地代の値上げを求められることもあります。
地主と借地人の双方の合意が必要なため、必ずしも値上げの要求に応じなくても構いません。というのも、地代の値上げには正当な理由が必要になります。土地周辺の利用価値、地主自身の経済状況、また固定資産税の増加などは正当な理由に当てはまりますが、それ以外の理由で地代が値上げされた場合は、正当なものかどうかを判断しましょう。判断しづらい場合は、専門知識を持つ不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
仮に地代や更新料の支払いを拒否することができても、地主との関係が悪化してさらなるトラブルに繋がる可能性もあるでしょう。
第三者に売却しにくい
借地権付きの建物を売却する場合、借地借家法の規定により、必ず地主の承諾を得る必要があります。
これは、地主と新しい借地権者との間で信頼関係を築く必要があるためです。地主の承諾が得られない場合、売却自体ができなくなります。
また、借地権付き建物は、建物の増改築やリフォームにも地主の承諾が必要となります。
これは土地の利用方法が制限されることを意味し、将来的な建物の改修や用途変更が難しくなります。
このような制約があるため、一般の不動産市場では買い手が限定され、売却価格も所有権付き物件と比べて低くなる傾向にあります。そのため、売却を検討する際は、これらの制限を考慮に入れた計画が必要です。
借地権に関する気になる疑問

最後は、借地権に関するよくある疑問を3つご紹介します。
借地権で起こり得るトラブルとは?
一概には言えませんが、借地権で想定されるトラブルには以下のようなケースが考えられます。
- 立ち退きを要求される
- 地代が値上げされる
- 更新料を請求される
- 地主が売却やリフォームを許可しない
- 契約更新を拒否されて借地権の返還を求められる
- 借地権の相続で揉め事が起きる
- 借地権を共有財産とすることで起こるトラブル
- 借地権の登記に不備があり契約解除になる
借地権は複雑であり、地主と借地人それぞれで法律を完璧に理解することは困難です。お互いの勘違いから、トラブルに繋がるケースがあります。話し合いや交渉による解決が難しい場合は、不動産会社や弁護士へ相談するとよいでしょう。
借地権の売却相場はどのくらい?
借地権付き建物の売却価格は、所有権付き建物の6〜8割程度が目安です。たとえば所有権付き建物の売却価格が5000万円なら、借地権付き建物の売却相場は3000〜4000万円になります。
ただし、借地権の売却には地主の許可が必要です。
旧借地権を買ってはいけないと言われる理由は?
旧借地権を買ってはいけない、と言われる理由には下記のようなケースが挙げられます。
- 大規模なリフォームや建て替えに地主の許可が必要
- 地代や更新料を支払う必要がある
- 融資を受けにくい
旧借地権を購入しても、一つひとつの活動に対して地主の許可が必要であり、制約が多いデメリットがあります。他にも、所有権付き建物に比べて価値が低く融資が受けづらくなること、また借地権の売買は地主と借地人がトラブルになるリスクがあることを理解しておきましょう。
まとめ
借地権は、地主から土地を借りて地代を支払い、借りた土地に建物を立てられる権利を言います。そして借地権には物権である地上権と、債権である賃借権の2種類が存在しており、それぞれで主張できる権利やルール、存続期間が異なります。もしも借地権を利用して建物を建てたい場合は、借地権の内容について理解しておかないと地主とのトラブルになりかねません。また、手頃な価格で販売されている建売には借地権が付いていることもあります。借地権が付いている場合、土地の所有者は地主にあることを強く認識しておきましょう。
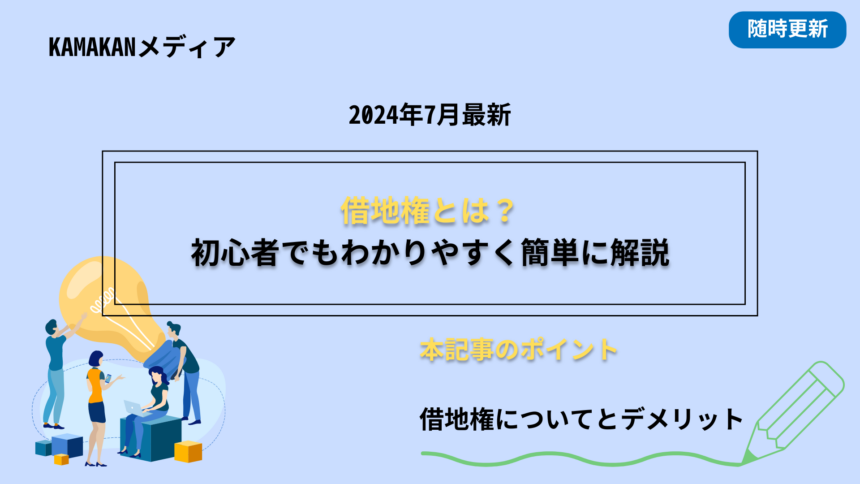
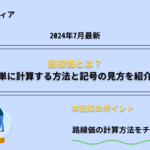
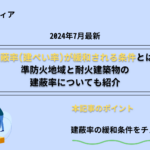
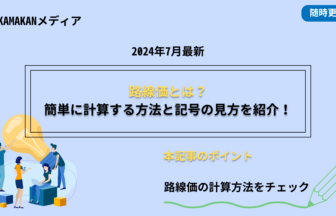
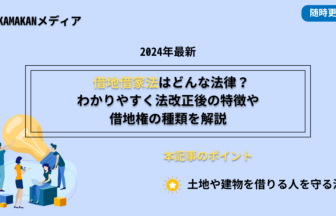
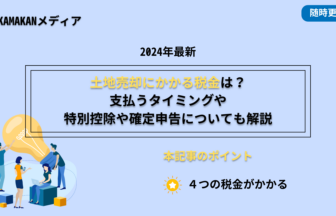
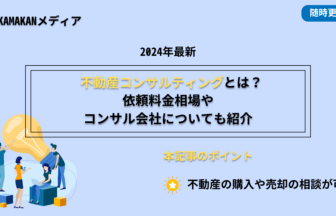
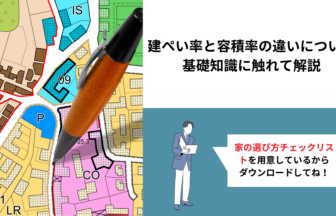




この記事へのコメントはありません。